パリ協定とは何?どんなことが定められているの
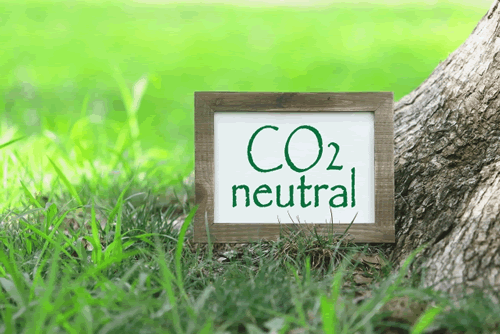
パリ協定は、2015年にフランスのパリで開催された国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の締約国会議(COP21)で採択された地球温暖化対策に関する国際的な枠組みです。
この協定は、気候変動による被害を最小限に抑えるために、各国が協力して温室効果ガスの排出を削減し、地球全体の平均気温上昇を産業革命前と比較して2度未満、できれば1.5度未満に抑えることを目指しています。
特に、気候変動の影響を最も受けやすい発展途上国や小島嶼国の状況に配慮し、すべての国が自国の事情に応じて具体的な行動計画を作成し実施することが求められています。
パリ協定では、各国が削減目標を自主的に設定し(これを「国が決定する貢献(NDC)」と呼びます)、それを5年ごとに見直して強化する仕組みが定められています。
この自主性が認められる一方で、目標の設定や進捗の透明性を確保するための国際的な報告・レビュー制度も導入されています。
また、気候変動の緩和だけでなく、その影響に適応するための対策や、先進国が発展途上国を支援するための資金調達の枠組みも盛り込まれています。
具体的には、先進国が2020年までに年間1000億ドルを動員するという目標が掲げられ、これを達成することで発展途上国の温暖化対策や適応策を支えることが期待されています。

日本はパリ協定に積極的に賛同し、国内外での取り組みを進めています。
日本政府はNDCとして、2030年までに2013年比で温室効果ガスの排出を46%削減する目標を掲げており、これに加えて50%削減を目指す「挑戦的な目標」にも取り組む意向を示しています。
具体例としては、再生可能エネルギーの導入拡大、電力の脱炭素化、ゼロエミッション車の普及促進、建築物の省エネルギー化、さらには水素社会の構築といったさまざまな政策が推進されています。
また、技術協力や資金援助を通じて、アジア諸国をはじめとする発展途上国の脱炭素化を支援しています。
一方で、パリ協定に対する各国の対応や姿勢は一様ではありません。
アメリカはトランプ大統領が同協定からの脱退を表明したことで、世界的に大きな波紋を呼びました。
トランプ大統領が脱退を決定した主な理由は、協定がアメリカ経済に不利益をもたらすとの考えに基づいています。
具体的には、パリ協定に基づく温室効果ガス削減目標の達成がアメリカの産業や雇用に悪影響を与え、特に石炭や石油などの化石燃料産業が打撃を受けると主張しました。
また、トランプ氏は協定が中国やインドといった発展途上国に対して過度に寛容であり、先進国であるアメリカに不公平な負担を強いるという点にも不満を表明しました。
この背景には、トランプ政権が「アメリカ・ファースト」を掲げ、国内経済の成長やエネルギー自立を重視する政策を推し進めていたことが大きく関係しています。
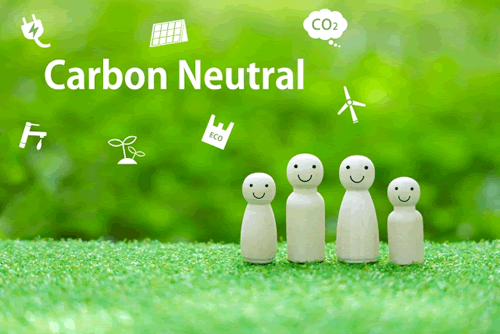
世界が気候変動に対処するためには、政府だけでなく企業や市民社会の参加も重要です。
例えば、日本では多くの企業が「カーボンニュートラル」や「RE100」といった目標を掲げ、事業運営において再生可能エネルギーを活用したり、サプライチェーン全体の脱炭素化を進めたりしています。
また、消費者レベルでも、再生可能エネルギーを利用する選択肢が広がり、省エネルギー家電の普及や公共交通機関の利用促進といった取り組みが進んでいます。
これらの動きは、パリ協定の枠組みの下で各国が努力を重ね、世界全体で気候変動問題に立ち向かおうとする意志を反映しています。
パリ協定は気候変動問題に対する国際社会の結束を象徴する重要な枠組みです。
温室効果ガスの排出削減という課題は極めて困難であり、実際には多くの政治的・経済的な障壁が存在します。
しかし、パリ協定の目標を達成するためには、政府だけでなくあらゆる主体がその役割を果たし、国際的な協力の中で解決策を模索し続けることが求められています。




